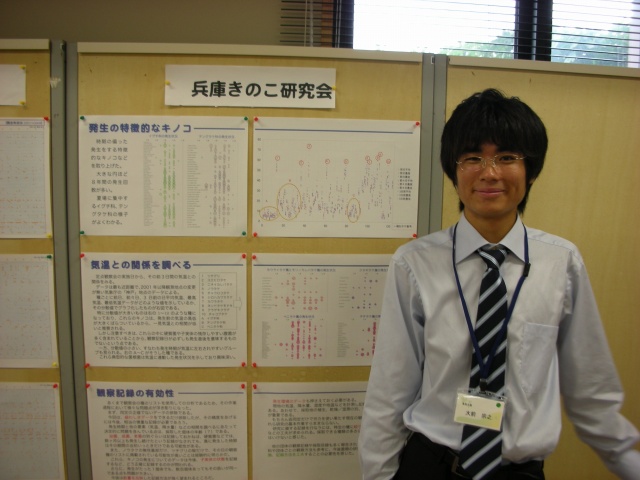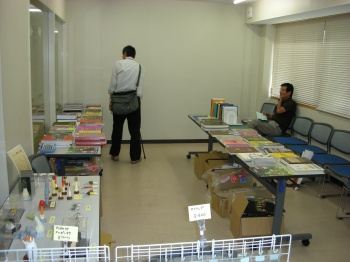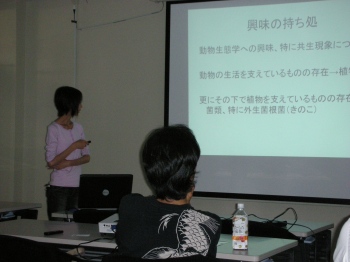|
日本菌学会第53回大会(鳥取)に参加して |
|
2009年8月20〜22日 文・写真/買うとく |
|
代表!!ポスター展示しかと完了しました
|
|
ある日突然電話がかかってきました。 「はい」 「申し込んどいたで」 「えっ何がですか?」 「若手の会の発表」 「????」 「何ですか?それ」 「菌学の道を歩んでいる若手で集まって発表するらしいねんて。それに申し込んどいたから!」 「いや、聞いてないですよ!いやいやちょっと待ってくださいよ。だいだい、いつなんすか?」 「菌学会の次の日」 「2週間後じゃないっすか!無理っすよ」 「いや俺もO田さんに発表することに半強制的に同意させられたんや!だから、2人で申し込んどいた。」 「なぜ、道連れに・・・」
これは菌学会に参加する2週間前のさんじょう氏との会話です。 今年の菌学会はさんじょう氏ともにお気軽な旅行気分で行く予定が前途多難となってしまいました。 |
|
さて、今年の菌学会の大会は鳥取大学で行われます。鳥取大学というと菌類関係では1、2を争う大学です。また、近くには菌じん研究所があり、日本の菌類は鳥取を中心に動いているといっても過言ではありません。 そんな鳥取大会ですが、本当は5月に開催される予定でした。しかし、兵庫県で猛威をふるったインフルエンザのため中止となり、8月20,21日の日程になってしまいました。この8月20,21日というのは木、金曜日と平日で、しかも、盆明けということで一般のサラリーマンの人には非常に休みにくい最悪の日程です。 延期になったとはいえ日程を決めた関係者にはもう少し考えていただきたいなと強く思いました。 |
|
8月20日
鳥取は神戸からバスで3時間ぐらいと以外にはやく着きます。 前々回参加したつくばに比べればまったく苦になりません。 現地につけばまず宿探しをしないといけませんが、前もってホテル「おおまえ」を予約していたので大丈夫です。 ホテル「おおまえ」の良いところはフロ、トイレ着きでホテル代がなんと無料です。ただし、支配人と同じ部屋で寝ることになります。 大学前にて支配人みずからお迎えがあり、ホテルで少し休息を取り、支配人の案内でさっそく鳥取大学へと向かいました。
大学には13時すぎに着きましたがすでに、シンポジウム等が始まっていました。 しかし、私たちはそれを聞くことは許されません。それを無視してアマチュアのポスター展示室に向かいました。当会の代表より「展示できなければ切腹!!」と大事な信書を預かっていたからです。 支配人との協力によりなんとか無事に信書を展示することができました。
あーだこーだしているともう、一般講演の時間です。 牛島氏らによる「ネッタイヌメリタケの分類学的再検討」からはじまりました。分類学的再検討というのは、DNA解析による分類学的再検討といえます。形態分類になじんでいるアマチュアの私たちにとっては「???」というような内容で困惑しました。 この内容だけでなく、全体的に言えますが、ほとんどがDNA解析の結果「こうなりました」というような研究結果が多かったです。
しかし、その中で一番興味があり、わかりやすかったのがこれです。 折原貴道氏らによる「シクエストレート担子菌コイシタケおよびその近縁種の形態学的評価と系統進化」 シクエストレートとは地下生菌と同様の意味です。 DNA解析が絶対というように感じられる内容が多い中、この発表はDNA解析を使うのですが、それはあくまでも1つの手段であって、DNA解析行い、これとこれは別種ならではどこに違いがあるのかをあらゆる角度から観察して分類するというような内容です。あらゆる角度とは形態学的、生態学的な視点などです。こういう視点から分類するのなら私たちにも十分可能であり意味があります。 また、腹菌類というその系統進化がよくわからなかった菌群をDNA解析で解明し、今までなぞだった部分を解き明かし、興味深い内容でもありました。 コイシタケがベニタケ科のキノコとなるようです。ベニタケ科の胞子はアミロイドですが、コイシタケはそうではなく、腹菌化とする過程でなくなったのではないかという仮説もありました。アミロイドという性質がキノコの生態としてどういう意味があるのかそれにせまることができるかもしれません。
一般講演も終わり、次は懇親会です。大学の食堂にて行われました 乾杯前のなが〜〜い挨拶のあとで乾杯! 残念ながらビールはぬるくなっていました。 ここで、著名な先生方と名刺交換を行い終了。
次は菌類懇話会の後藤さんらによるアマチュアの会の懇親会です。 幹事は当会でO田さんでした。お疲れさまでした。
|
||||||||||||||
|
8月21日
この日は午前から一般講演です。 この日も興味深い内容がめじろおしです。 つくば大会のときにも名前をあげましたが、今回も ◎白水貴氏らによる「アカキクラゲ綱における新目Uniacrymalesの設立とCerinomycetaceae科の再定義」、 ◎早乙女梢氏らによる「日本産Poluporus pseudobetulinus複合種の分類学的検討」 の発表は大変聞きやすく、わかりやすい内容でした。 そんな中、急遽来れなくなった工藤伸一氏のかわりに長沢先生が発表されていたのが印象的でした。
さて講演も終盤にさしかかった頃、当会のエース2人が発表します 奥田彩子らによる「イワウメ科オオイワカガミおよびイワウチワの菌根共生」 廣瀬俊介らによる「ブナ林におけるギンリョウソウ及びウメガサソウの菌根共生の実態」 2人ともかなり緊張している様子が伺えました。偉い先生方がいる中での発表は緊張して当然です。ですが、聞き苦しいこともなくよかったと思います。しかし、菌根というものをまったく理解していない私にとっては難しい内容でした。もっとキノコ以外のことも勉強したほうがいいなと感じました。 とりあえず、お二方ともお疲れさまでした。
講演終了後、根田仁博士と話しをする機会を得たのは収穫です。いろいろと楽しい話を聞かせていただきました。
夜は私とさんじょう氏と、支配人とO田女氏とO原氏の5人で食事に行きました。 たぶんO田女史はかなり飲んでいたと思います。酒豪だったようです。
食事後ホテル「おおまえ」に戻り、とりあえず、全員であやしいものがないか家宅捜索を行いました。 支配人の慌てた行動がとてもおもしろかったですね。 ミニスライド会をしましたが、O原氏は即興でパワーポイントによるスライドを作ったことにびっくりさせられました。 できる人は仕事がはやい!! お互いに興味深い情報交換有意義な時間でした。
|
|
8月22日
この日は若手の会の発表会です。 若手の会とは大学にて菌学を志している学生が集まった会で、本日はその人らによるスライド発表があります。 参加者はO田女史、支配人、白水氏、折原氏らです。 なぜ、このような会に私とさんじょう氏が参加できたのでしょうか? とりあえず私とともにさんじょう氏は「若手」と認められたようです・・・ですが、こういう場に参加させていただけるのはありがたいことです。
9時スタートでしたが、支配人はトップバッターであったにもかかわらず、「どうせ時間通りにやってないですよ」と言って遅刻。 残念ながら時間どおりにはじまっており、彼は順番を飛ばされていました。 非常に残念です。
正式な発表ではないということで、みなさん普段いえないような自由な発想、今後の展望などを発表していました。 さんじょう氏の「アミガサタケを考える」 はキノコを知らない人も参加していたのですが、かなり公表を得ていたように思います。 私はHPにも掲載している「日本きのこ目録」の苦労談的な話で、2週間前の知らせであったため、大した内容ではありませんでした。言い訳ですね。でも、「一体私は何を発表したらいいんだ!」と結構悩んだのですよ。大した内容ではないうえに、時間をオーバーしてしまったことはとても許されることではありません。 世話役の白水さんすいません。
発表会終了後、若手の会で食事に行き、交流を深め、その後、名残惜しくも私とさんじょう氏は鳥取をあとにし、神戸へと帰宅しました。
|
|
菌学会での発表は難しいものも多いのですが、中にはわかりやすい内容のものもあったりします。 でも、一番いいことは普段話せないような全国各地の人と話す機会があることです。 今回も話をしてみたいと思ったかたと交流することができ有意義な3日間でした。 また現地でお世話していただいたO前、O田の両氏には大変感謝しております。
来年は東京で菌学会の大会が開催されるようです。 菌学会大会となると堅苦しく考えてしまいますが、そうでもないので、菌類に興味がある人は参加することをお勧めします。また、来年も参加できればと思います。
|